Story
(小説)
はちみつのにおい
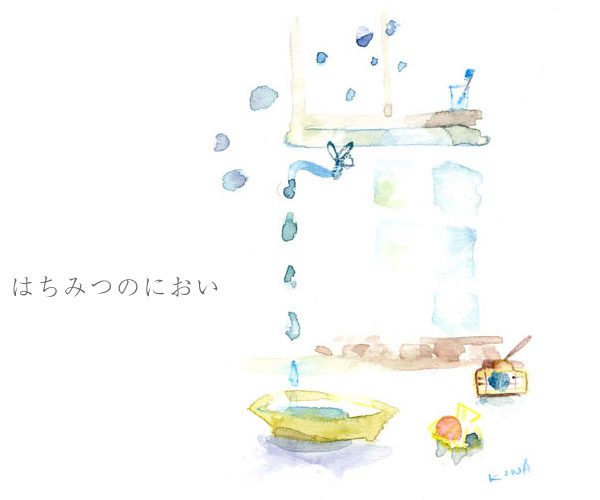
~prologue~
私は物持ちのいいほうだ。
みっちゃんからもらったポーチも、小学校のときにユキちゃんからもらった桜色のマグカップも、
もう何年もするのに大事に使っている。時々それが本人に見つかって、びっくりされるぐらいだ。
今日は、はちみつの香りがした。
どうやらこの石鹸には、はちみつが練りこまれているらしい。
だけど私はこういう贈り物にいつも少々困ってしまう。
大事にしたいのに、使うと小さくなってしまうから。
これから毎朝、だんだんと小さくなっていく石鹸をみながら、いつも少しだけ悲しくなるのだ。
和麻(カズマ)は、はちみつが好きだった。
コーヒーでもパンでも、何でもはちみつを使った。
だから私も真似をしてはちみつを使った。
そんな和麻は、私の前からふっと消えていった。
小さなカエルのぬいぐるみを残して。
「赤い庇のあの店で見つけたから。」
そう言って笑っていた。
今振り返ると、和麻と一緒にいた日々はとても幻想的なのだ。
それは私のとても綺麗な部分としてほのかに甘い香りを残しながら、今も心に残っている。
はちみつの香りのように。
∮ 雨の彩り ∮
「どこかいこうよ。」
「だけど、今日は雨だし、寒いよ。」
「しんちゃんといるときはいつも雨だもの。どこにもいけないよ。」
そういって結局、私たちは家の中にいた。雨が降っているので、私は窓越しに外ばかり見ていた。
しんちゃんは壁に絵を描く仕事をしている。
しんちゃんの仕事は屋外での作業がほとんどだから、雨の日は突然休みになることが多い。だから決まってしんちゃんは雨が降ってからいつもひょっこり私の家に来た。
「昔から広いところに絵を描くのが好きだった」といつもしんちゃんは少し目を細めながら私に話す。
都心から離れた静かな住宅街にあるしんちゃんの実家は、幼い頃から彼の恰好のお描きスペースだったらしい。前に一度訪れたそこは、地味な平屋建ての母屋とは対照的に恐ろしくカラフルな塀と壁面に覆われていた。
私はよくしんちゃんが絵を描いている場所へ訪ねて行く。そこにはしんちゃんがいて、大きな壁があって、たくさんの塗料缶や刷毛、そして辺りにはポタポタと色んなペンキがこぼれていて・・・。
青い空が額縁の大きなキャンパスに臆することなく堂々と立ち向かっているしんちゃんは、その広い広い世界を独り占めしている。そしてそれをこっそりと後ろから覗き込んでいる私は真っ白いつるんとした子どもみたいだ。その中で繰り広げられる、色、色、色たちの神秘的な交わりを目の当たりにして、毎回夢中になる。
たぶん私はきっと、絵を描いているしんちゃんと、しんちゃんを中心とするその風景全体が好きなんだ、と思う。
しんちゃんと出会った初めての日も、彼は壁に絵を描いていた。
確かあのときも私はしんちゃんの横顔とその光景に見惚れ、思わず足を止めたのだ。
「そうやなあ、雨ばかりやな。いつもごめんな。」
しんちゃんの申しわけなさそうなその声はもう何度も聞いている。
「でも私、昔から雨の日は結構好きなの。」
そういうとしんちゃんは不思議そうに私の顔をみて、そして嬉しそうに笑った。
雨の日特有のどこか閉ざされたような空気の中、窓ガラスを伝う水滴を目で追いながら、しんちゃんの唐突の休日を部屋で過ごす。
私の住んでいるところは五階で、今日みたいな日はここに越してきてよかったと思う。雨の日は外を見れば色とりどりの花が咲いているから。私の背の高さでは分からない花がここからだと分かるのだ。
・・・《傘の花》
「しんちゃん。綺麗だよ。」
「本当だ。」
水色、黄色、紺色、赤・・・
五階から見下ろすその花は、すれ違い、近づき、そしてまた離れていく。
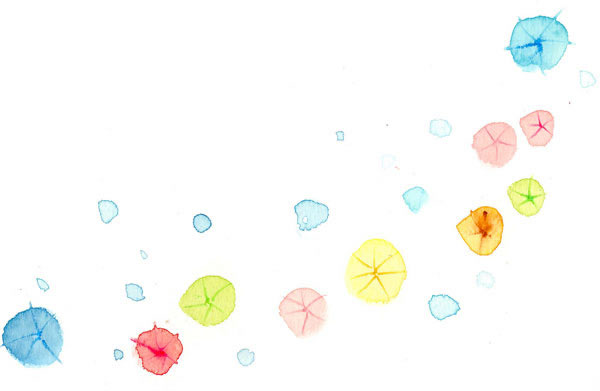
幼い頃、しとしとと降る雨の日はよく縁側に座っていた。
友達のナオちゃんともみいちゃんとも外で遊ぶことができないから、仕方なく私は外を眺めていた。
私の実家は、縁側に出る大きなガラス戸の傍に大きな紫陽花があり、いつも梅雨時期になると紫色の綺麗な花を満開にさせて私の部屋を覗いていた。子どもの顔ほどある大きなその花が、頭を一生懸命もたげながら私の方を見ているような気がして、私はいつも「がんばって」と心の中で応援した。
それにだ。雨の日は水滴がまるで宝石のように葉の上に落ちる。私はきらきらと光るその粒を見ながら、いつしか雨の日は好んで窓の傍か縁側にいた。
緑たちが、雨のしずくでおめかしするのだ。
そして、ほのかに香る土のにおい。
大人になったら東京に出てきたりしたから、そのわくわく感は減ったけれど、今はしんちゃんが雨の日は決まって私の傍にいるし、それにもうひとつ、雨の日の彩を発見することができたから、私はすごく幸せ者なのだ。
そんなことを思いながらしばらく窓の外を眺めていると、私はいつの間にかひとつの赤いいちご柄の傘を目で追っていた。
「ねえ、しんちゃん。あのいちごの傘、さっきからずっとここの下にいるね。」
「ん、どの傘?」
「ほら、あの自販機の横に。」
「ほんまや。かわいい傘やな。」
きっと音楽でも聴きながら立っているのだろう。その傘は左右にゆっくり揺れながら、時々クルクルと回っている。
「私、ああいういちご柄好き。今はちょっともう可愛過ぎてなかなか持てんけど。ああいう可愛い柄が女子の心をきゅうんとさせるんよ。」
「ふうん。」
窓ガラスに付いている水滴が傍の白いカウンターに、水玉模様の淡い影を落としている。しんちゃんは片肘を付いて外を眺めながら、右手でコーヒーを啜っている。
クルクルクル。
いちごの傘が回っている。
きゅううん。
慌しく流れる色たちの中で、その傘だけがゆっくりとその場で泳いでいるようだ。
きゅうううん。きゅうん。
胸の中の奥の奥、そこに響く高い音が私の鼓動と重なって擽った。
ドキンドキンドキン、きゅううう。
その時突然、そこだけ時が止まったかのように、そのいちごの傘はぴたっと止まった。
同時に私の胸の奥の高い音も止まり、残された鼓動だけが私の中で速く響いている。
その時の私はいちごの傘から目を離すことができなくなっていた。
しばらくすると、その傘はゆっくりと折りたたまれ、そして、その下から真紅の口紅をつけた目の大きな少女がゆっくりと上を見上げた。
思わず息をのんだ。
雨で綺麗な髪が濡れているというのに、その子はただ立ち止まって私の顔をじっと見ていた。赤い長靴がかすかに記憶にある気がしたのは、私も幼い頃いつも好んで赤い長靴を履いていたからだろう。
私の脳裏にはとても甘く優しい何かが流れた。そして、そのあと急に胸が締め付けられるような衝動にかられ、しんちゃんにしがみついた。
「ミサ?」
私はしんちゃんの胸に頭をうずめた。
雨音以外は、時計の秒針音としんちゃんの鼓動。静けさの中に一定の間隔で刻む音と、伝わってくるそのぬくもりが、ゆっくりゆっくり私を静めていく。
しんちゃんがそんな私をみながら不思議そうにフフフと笑った。
きゅきゅきゅるん。再び音が聞こえる。
そう、この笑顔。しんちゃんのこの笑顔を私は見逃すまいといつも必死になるのだが、その時だけはしばらくの間、しんちゃんと自分の鼓動を聞いていた。

時計をみるといつの間にかもう正午をまわっている。
さっきのはなんだったんだろう・・・。
もう、大丈夫だ。
いつもと何かが違う、自分でもよくわからない感覚に私は少し戸惑いを覚えつつ、そのままずっと私を抱えてくれているしんちゃんの顔を見上げ、「お腹がすいたよ」と言った。しんちゃんは何も聞かない。変に詮索しないのはいつもと同じ。そういうところも私は好きだった。
あったかい、湯たんぽのような人。
「そうだな」と笑ってしんちゃんは立ち上がり、そして私たちはいつもどおりじゃんけんをした。
今日はしんちゃんが負けたので、私はちょっと肩を落とした。
じゃんけんをする決まりを作ったのはしんちゃんだ。私だけに料理を作らせるのは悪いと言うしんちゃんの心配りからなのだが、しんちゃんの料理より私の料理の方が断然、おいしいのだ。
しんちゃんは台所からパスタを茹でて持ってきた。そして、それに冷蔵庫から出した納豆をかけた。
「かんせーい♪ 納豆パスタ。」
そういってしんちゃんはにっこり笑う。
「納豆は身体にいいんだよ」という理由からそのレシピは頻繁に出てくる。しんちゃんが作れるものはそういったレベルのものがほとんどなのだが、悪気のないその笑顔に、私はいつもつられて食べた。
私が風邪を引いたときも、しんちゃんはいつも慌てて何か作ろうとするのだけれど、結局冷蔵庫の中のものをそのままかけただけのパスタで、私はいつも笑ってしまう。
ちょっと物足りない昼食を終え、また私は窓辺の椅子に座った。
あの傘の少女は、もういなかった。
斑に行き交う傘の花をまた目で追いながら、しんちゃんのパスタがあまりにもお粗末だったので、私はもう夕飯のことを考えていた。
「しんちゃん、夕飯何にする?」
「いま食べたやん。」
「でも夕飯、何食べたい?」
「そんなこと考えられない。」
「うーむ。」
真剣に考え込んだ私をみて、しんちゃんが後ろでくすくす笑った。しんちゃんのごつごつした手が私の頭を撫でた。
「じゃあ、あのコートヤードの店に行くか?」
「うん!」
私は嬉しくなって、お気に入りの傘を用意した。
☆
「そういえば、ミサ。俺、好きな子ができたよ。」
しんちゃんはチキンを食べながら、とても嬉しそうに言った。雨が降っているせいかお店はカランと空いていた。
赤い電車の後に「元町・中華街」と書かれた紫色の電車が通るのを眺めながら、私はぼんやり中華でもよかったかななどと考えながら、そう驚きもせずに答えた。
「どんな子?」
「ああ。」
少しの沈黙のあとにしんちゃんはさらりと言った。
「さっきのあのいちごの傘の女の子。」
もう何回目だろう。
しんちゃんはいつも無邪気な笑顔で私にそう言う。何もためらいがないので私のヤキモチもどこか間違っている気がしてしまうから、しんちゃんはすごいと思う。
でも今回だけは違っていた。
「・・・」
「でさ、その子を俺の部屋にしばらく住ませたいんだけど・・・。」
「まって、しんちゃん。」
「ん?」
「それ、おかしい。」
「なんで?」
「なんでしんちゃんがその子を住ませてあげるの?」
「なんやよくわからん子で。」
「だから?」
「だから、なんか目、はなせんようになって。」
「それで?」
「少し住ませてあげようかと。」
「・・・」
しんちゃんからの突拍子もない告白は結構慣れっこだった。
しんちゃんが好きな子が出来たということは、よくあることだったし、そしてそれはいつも恋愛のそれとはちょっと違うということも分かっていた。いつも何らかの理由があり、人助けのようなときもあれば、本当に好奇心だけで気になった子だったりするときもある。はじめこそ心配はしたものの、私の傍で笑っているしんちゃんをみていると、いつしかそういうヤキモチの類の心配は無駄だというそんな気持ちになってしまった。結局心のどこかで私はしんちゃんを信頼しているのだと思う。
だからいつもなら出てこない感情、怒りとか驚きとかそんなものでもなく、心の底から湧き上がってくるなにかが、私を混乱させた。
「私もしんちゃんの部屋に住みたいって言ったら?」
「いいよ、住んで。」
「まって。」
「ん?」
「しんちゃんの部屋って狭いやん!そんなの無理や。」
涙ぐむ私をみて、さすがのしんちゃんも慌てたようで、結局最後にこう言った。
「よ、よし、じゃあ、ミサの家に住もう!」
初夏の風が吹く頃から、私たちは三人暮らしを始めた。
「はちみつのにおい」第一話 ~雨の彩り~
NEXT→【第二話】